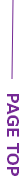11月8日に万博記念競技場(大阪府)で2025関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1、対甲南大戦(REDGYANG)が行われた。序盤から試合の主導権を掌握し、44―9と大勝。最終節で待望の白星を挙げた。
第1Qは#22山本(法4)のキックオフでスタート。序盤から#44西村(経4)や#91馬込(法3)らディフェンス陣の好プレーが光る。開始4分、攻撃権を得た同志社は#14仲田(商1)を中心に攻撃を展開。強豪・関学大との一戦でTDに導き、自信を付けたルーキーが冷静にオフェンスを指揮した。泥臭く最後まで足を動かし続けることが強みである#24大島(理工2)と#32内藤(文情4)のランでファーストダウンを更新。開始6分半には仲田から#81吉森(スポ3)へのパスが通りそのままTD(タッチダウン)。「かなり練習してきたパスでもあったので、自信もあった」(吉森)。先制に成功した同志社は、その後もディフェンス陣が無失点に相手を抑え込む。第1Qを6―0で終えた。

第2Qは甲南大のフォースダウンが自陣11ヤードからスタート。FG(フィールドゴール)で3点を返されたが、流れを簡単に渡さないのが今試合の同志社だ。自陣28ヤードからの攻撃では、仲田のロングパスが#89小杉(社3)の手元にしっかりと収まる。エンドゾーン目前まで迫ると、最後は内藤が中央を突破し追加のTD。「小杉がしっかりとつなげてくれたのであとはOLが空けてくれた道を走るだけでしたけど、うれしかった」(内藤)。PATも#10平野(理工3)が確実に決め、7点を加えた。相手に攻撃権が移ると#35三島(理工4)がインターセプトを決め、敵陣45ヤードからのチャンスを創出。セカンドダウンで#13樋口(商4)が鋭いランで大きくゲイン。「フィールドに戻ってプレーすることを想像しながらリハビリしてきて、素直に今普通にプレーできていることに幸せを感じる」(樋口)。開幕戦でけがからの復帰を果たした樋口がチームを鼓舞した。開始3分半には内藤が右サイドを駆け抜け、再びTD。勢いそのままに、開始9分には#86羽入(スポ3)が自陣10ヤード付近で相手パントをキャッチし、そのまま独走。パントリターンTDを決めた。しかし残り2分で自分たちのミスから失点を許す。それでも直後に#88三浦(商2)が約93ヤードのキックオフターンTDを決め、再び同志社サイドのボルテージを高める。「みんながしっかりとブロックしてくれてたので、あとは走るだけだった」(三浦)。34―9と大きくリードを広げ、前半を折り返した。

第3Qは相手のキックオフでスタート。ディフェンス陣が鍛錬の成果を遺憾無く発揮し、ファーストダウン更新を許さない堅守を見せた。だが一方で、オフェンス陣は今季課題とされてきた後半で勢いを欠くという弱点が顔を覗かせる。それでも残り2分、自陣48ヤードからの攻撃で意地を見せた。仲田から三浦、吉森へのパスが次々と通り、敵陣35ヤードまで前進。相手に流れを渡さぬまま第3Qを終えた。
第4Qは敵陣35ヤードから同志社のファーストダウンが再開。セカンドダウンで仲田が自らボールを持ちフレッシュを獲得。続くサードダウンでは、#87脇田(スポ4)へのスクリーンパスでゲインするも、あと一歩届かずフォースダウンへ。ここで同志社はFGを選択し、#38後藤(商2)が37ヤードの距離を豪快なキックで成功させた。キックオフ後、すぐにディフェンス陣が相手の攻撃を断ち切り、再び攻撃権を得る。開始5分、ハーフライン付近からの攻撃で内藤がランで一気に敵陣34ヤードまで迫った。続いて仲田から三浦へのパスが通り、そのままエンドゾーンまで駆け抜けTD。チームはリードをさらに広げる。終盤は、三島がこの日2度目となるインターセプトを決めるなど、ディフェンス陣が最後まで集中力を切らさない活躍を見せた。試合終了のホイッスルが鳴り響き、スコアは44―9。ODKで支え合い、ワイルドローバーが圧巻の勝利を飾った。

ようやくつかんだ今季初白星。「やっと勝ててうれしい気持ちと、もっと早く勝たなければいけなかった気持ちの両方がある」(三島)。長く勝利から遠ざかっていただけに、選手たちの表情には安堵と悔しさが入り混じっていた。また、「前半で点数を取れても後半で点数を取れないというオフェンスをまたやってしまった」(脇田)と依然として修正しきれない後半で失速するという課題点を前に選手たちの表情はどこか硬さが残る。現状に満足している選手はおらず、その目には早くも次戦への闘志がみなぎっていた。
「去年、一昨年と2部を経験して、このチームを日本一にしたいと思ってやってきた」(竹島)。リーグ戦7節を戦い抜き、選手たちの努力とは裏腹に1勝6敗で7位に終わったワイルドローバー。3週間後に控えるのは、同志社の未来が懸かった入れ替え戦。負けは許されない。「最後どうなってもいいいので、来年からも後輩たちを1部に立たせてあげたい」(加藤)。幾度もの悔しさが染み込んだユニホームに袖を通し、竹島組最後の一戦へ。決して平坦ではなかった1年間。その歩みが間違いではなかったと証明するために、最後の1秒まで死力を尽くす。
(文責・益野瑛真、宮本芽衣、撮影・シンウンス、桑原真桜)